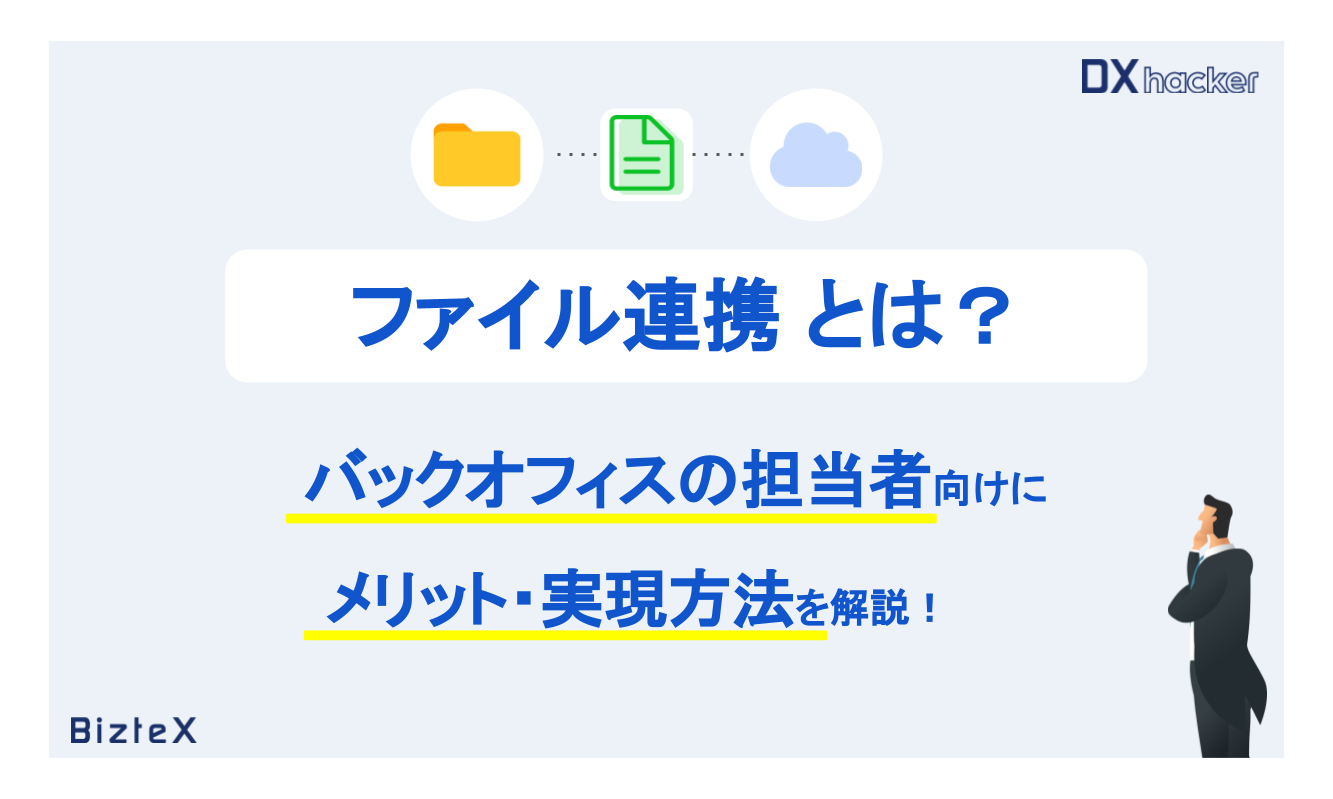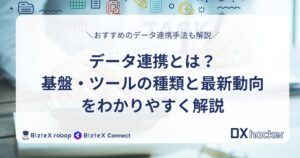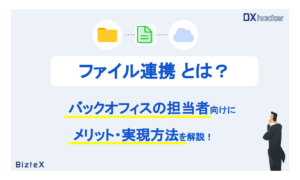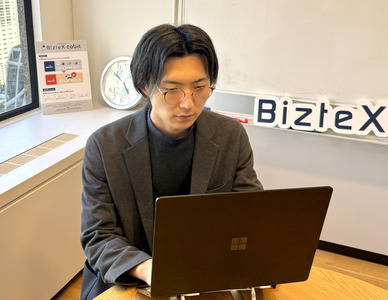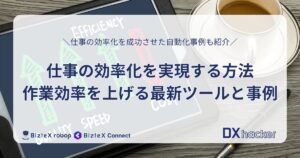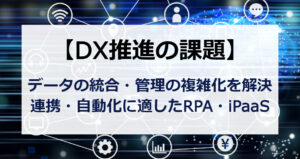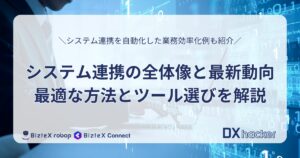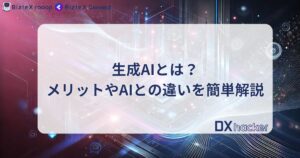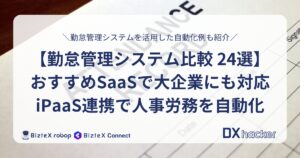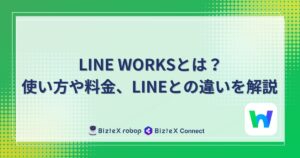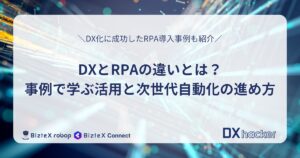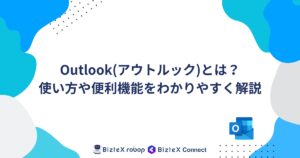さまざまなクラウドサービスが業務で利用されるようになった近年、データが断片化されてしまい、マスタ管理や横断的なデータ活用の面で、効率が低下してしまうケースも見受けられます。
そこで 本記事では、複数システムのデータを統合・連携するための手段として、ファイル連携について解説します。
「ファイル連携 とは何か?」「どのようなメリットがあるのか?」「具体的にどのように実現するのか?」といった内容について、バックオフィス業務の担当者の目線で、やさしく、わかりやすく解説します。
ファイル連携とは何か
ファイル連携とは、異なるシステム間でのデータの送受信を、ファイル経由で行う連携プロセスのことです。このプロセスにより、企業や組織内の情報共有が容易になり、データの一貫性や活用度が大幅に向上します。
例えば、営業部門と経理部門が異なるシステムを使用している場合、ファイル連携により両部門間の報告書や請求書の共有がスムーズになります。ファイル連携は組織全体のデータフローを最適化するための重要な手段です。
また、ファイル連携はシステム間の連携手段として長年利用されている手段であり、多くの実績がある技術であると言えます。
ファイル連携とデータ連携の違い
ファイル連携とデータ連携はしばしば混同されがちです。
というのも、Web上の記事や文書を見ると、データ連携という言葉は、大きく分けると2種類の定義で利用されており、文書によって意味合いが異なっています。
データ連携とファイル連携の違いについて、データ連携という単語がどのような意味で利用されているかと合わせて解説します。
①データ連携 = 「異なるシステム・アプリケーションが保持しているデータを共有し、有効活用すること」という意味の場合。
この場合、ファイル連携はデータ連携の方式の一つであるといえます。

データ連携の方式としては以下のようなものが存在します。
- データベース連携
- ディスク共有
- API連携
- ファイル連携
②データ連携=上記の「データベース連携」や「API連携」等を総じて呼ぶ場合
データ連携という単語は、「システム間のデータ共有方法のうち、ファイルやディスク等の媒体を介さずデータを連携する方法全般」を指す単語としても利用されることがあります。
この場合、ファイル連携とデータ連携はシステム間のデータ共有を実現する方式の一つであり、実現のために利用する具体的な技術によって区別されます。

\「結局使われない…」業務ツールの悩み、もう終わりにしませんか?/
ファイル連携が適した用途とは
ファイル連携は、システム間でデータを共有する際に「ファイル」を媒介として送受信を行う方式です。特に以下のような用途に適しています。
大容量データのやり取り
ファイル連携は、1つのファイルに大量のデータを格納できるため、一度に大容量データを送受信する場面で有効です。
一方でAPI連携は、システムの制約により一度に扱えるデータ量が限られるケースが多く、大量データの一括処理には不向きな場合があります。
ファイルそのものをデータとして扱う場合
システムにファイルをアップロードして保存する場合、多くはデータベース(DB)に直接格納するのではなく、ストレージに保存し、DBにはファイルの保存先情報のみを記録します。
契約書PDFや画像ファイルなど「ファイルそのもの」が業務上のデータとなるケースでは、ファイル連携が適しています。
バックアップを容易に残せる
ファイルは古くから利用されている仕組みであり、ほとんどのOSが作成・複製に対応しています。ファイル連携では処理前後に簡単に複製を作成でき、バックアップを残せる点がメリットです。
これにより、エラー発生時の再実行や、特定時点のデータへの復旧が容易になります。
人による確認や加工を挟める
ExcelやCSV、XMLなどのファイルは、専門知識がなくても一般的なソフトで内容を確認・編集できます。そのため、連携処理の途中で人の手によるチェックやデータ修正を挟みやすい点も特徴です。
自動化しつつ、人の判断や加工を柔軟に組み込める点で活用価値があります。
ファイル連携の強み
ファイル連携が他の連携方式と比べて優れている点を整理すると、以下の2つが大きな特長として挙げられます。
比較的容易に実現できる
ファイルを用いたデータの入出力や加工は、多くのシステムやアプリケーションで標準的に対応しています。特にCSVによるインポート・エクスポートは幅広いシステムで利用可能なため、連携の難易度が低く、導入しやすい方式です。
例えば、AシステムからCSVファイルをエクスポートし、Bシステムにそのファイルをインポートするだけで、シンプルにシステム間のデータ連携を実現できます。
データ項目の変更に柔軟に対応できる
ファイルを介したデータ受け渡し方式であるため、連携対象のデータ項目や種類が変更になった場合でも柔軟に対応可能です。
たとえば、AシステムとBシステム間でCSVの項目名が変更された場合でも、以下のような流れで修正できます。
- AシステムからCSVファイルをエクスポート
- Excelなどで必要な形式に加工・編集
- Bシステムにインポート
この加工工程は人手でも対応できるため、運用段階で項目変更が頻繁に発生するフェーズでも大きな負担をかけずに調整できます。結果として、保守運用コストの抑制にもつながります。
ファイル連携がもたらすメリット
ファイル連携によってシステム間でデータ共有が可能になると、以下のようなメリットが得られます。
情報の一元化による検索時間の削減と業務効率の向上
ファイル連携による情報の一元化は、必要なデータを迅速に見つけ出し、業務の効率化を図る上で非常に重要です。
例えば、営業資料、契約書、プロジェクト報告書などが異なるシステムに散在していると、これらのデータを探すために多くの時間を浪費してしまいます。
しかし、ファイル連携を適切に行うことで、異なるシステム間のデータを集約することで、一元的な管理・検索・データへのアクセスが可能になり、業務効率の向上を実現できます。
データ整合性の保持とエラーの減少
異なるシステム間でのファイル共有を効率化することで、データの整合性が保たれ、入力ミスや情報の重複などのエラーが減少します。
たとえば、顧客情報の更新があった場合、ファイル連携によりすべての関連部門が最新の情報にアクセスできるようになり、古いデータに基づく誤った判断を防ぐことができます。
チーム間コミュニケーションの改善と協働の促進
ファイル連携はチーム間のコミュニケーションを効果的に改善し、協働を促進します。
例えば、マーケティング部門と営業部門が共同でキャンペーンを行う際、ファイル連携によって両部門が同じデータを共有し、それぞれがメインで利用するシステム上で活用 できるようになります。
そうすることで、素早い意思決定や効果的な戦略立案が可能になり、チームの生産性向上に直接寄与します。
ファイル連携の実現に必要な3つの要素

ファイル入出力方法
ファイル連携を実現する大前提として、連携したいシステムそれぞれが、ファイル入力(インポート)・出力(エクスポート)機能を備えていることが不可欠です。
多くのシステムはCSVやExcelなどの形式でのデータ入出力機能を備えていることが多いですが、機能が存在しなかったり、一部のデータ項目はファイル入出力機能では扱えないケースがあったりすることもあるため注意が必要です。
また、ファイル連携を自動化したい場合、対象のシステムがGUIでの画面操作以外でのファイル入出力ができるか?についても重要な要素となります。
対象システムがGUI以外ではファイル入出力機能を持たない場合でも、RPAのような実際にGUI操作が可能なツールを用いることで、ファイルのインポートやエクスポートの自動化を実現することができます。
ファイル転送方法
システム間でファイル連携する場合、出力したファイルを連携したいシステムが取り込み可能な場所までどのように転送するかも重要です。
ファイルの容量や、転送処理の確実性、運用コストなどの観点で比較し、用途に合わせた手段を選択することが重要です。
ファイル転送の手段としては下記のような方法があります。
- メールに添付して送信
- Webサービス(チャット・クラウドストレージ等)を利用して共有
- ファイルサーバーを利用して共有
- USBメモリーやDVDなどの物理メディアで受け渡しを行う
ファイル形式・データ変換方法
異なるシステム間でファイル連携を行う場合、データやファイルの形式も統一されたフォーマットでは無い場合がほとんどのため、それぞれのファイル形式やデータの内容を揃えるための変換機能も必要になります。
| ケース | 必要なファイル形式・データ変換機能 |
| 連携元のシステムでは、CSVファイルとしてデータを出力するが、連携先のシステムではデータ入力可能なファイルはXML形式のファイルである | CSVファイルをXML形式に変換する機能が必要。 |
| 販売管理システムから、出力される販売実績データを会計システムに連携する場合、取引先毎に販売明細の金額をまとめる必要がある | 販売実績データのファイルを集計・集約し、会計システムがインポート可能な形式にデータフォーマットを変換する機能が必要。 |
ファイル形式・データ変換方法として以下のような手段があります。
システム側のファイル入出力機能の利用
システムによっては出力するファイルやデータの形式をカスタマイズする機能や、ファイルインポート時に項目のマッピングをカスタマイズする機能を備えているものがあります。
CSVの項目名の変更や、不要なデータの削除などの簡易な変換は、システムが標準で備えている機能によって対応可能な場合があります。
バッチ・Excelマクロ等プログラム開発
ファイル連携の自動化で多く利用されている手段として、簡易なプログラムでデータ変換を行うというものがあります。
複雑な変換処理が可能ですが、その分開発の難易度はあがるため、開発コストや、改修時等の保守運用コストが高くなる場合があります。
手作業
人間が対応するため、開発が不要で容易に実行でき、最も複雑な変換処理にも対応可能で、連携仕様や運用の変更などにも柔軟に対応ができると言えます。
一方で複雑な処理やデータ件数が多い場合、プログラム等と比較して作業時間がかかり、ヒューマンエラーによるミスも発生を防ぐことが難しい手段であるといえます。
ツールの利用(RPA・ETL・iPaaS)
プログラム等を利用する場合と比較すると、細かいカスタマイズや複雑な処理などの場合はやや対応できないケースもありますが、開発・運用にかかる学習コストは低く、高度な処理も比較的簡単に開発することができます。
また、ログ管理やエラー通知などの機能も標準機能として備えているため、運用フェーズになってからの稼働監視の仕組みの構築や、不具合発生時の原因特定などの保守運用にかかる対応コストを削減することが可能です。
ファイル連携を実現するには?6ステップで課題を解決
ここまで紹介してきたように、ファイル連携には様々なメリットがありますが、実現するには、技術面や運用等、考慮すべきポイントがあります。
ここでは、ファイル連携を実現するための具体的な検討プロセスについて紹介します。
①目的を明確にする
ファイル連携の目的を明確にすることは、プロジェクトの成功に不可欠です。
たとえば、製造業での利用を考える場合、設計部門と生産部門間の設計図書の共有を効率化することが目的となるかもしれません。
設計図書の更新情報が共有されることで、生産ラインの遅延や誤作業を防ぐことができます。
このように、目的を具体的に設定することで、ファイル連携がもたらす具体的な改善点を明確にし、効果的なプランニングが可能になります。
②目的を達成するための要件を明確にする
目的を達成するために必要な要件を明確にします。
例えば、機密情報を含む法務部門の文書管理では、セキュリティが最優先事項となります。この場合、ファイルの暗号化やアクセス権限の厳格な管理が必要です。
また、営業部門が顧客情報を共有する際には、アクセスの容易さとデータの正確性が重要になります。このステップでは、それぞれの部門や業務ごとの特性を考慮した要件定義が求められます。
③要件を達成するための手段を調査する
市場には多様なファイル共有ツールやデータ管理システムが存在します。
例えば、大量のデータを頻繁に共有する必要がある場合は、高速で大容量のデータ転送が可能なツールを検討する必要があります。また、リモートアクセスが頻繁に必要な環境では、クラウドベースのソリューションが適しているかもしれません。
時にはメーカーの製品提案を受けたり、社内のシステム部に相談する等、その道のプロからの情報・知見を得ることも重要です。この段階では、各ツールの機能、コスト、使いやすさなどを比較検討します。
④手段を元に実現案を作成する
調査した手段を基に、実現案を作成します。この際、予算の制約、必要なリソース、実装までのタイムラインなどを考慮に入れます。
例えば、予算が限られている小規模企業では、コスト効率の高いクラウドサービスが適しているかもしれません。また、スタートアップや新規事業など頻繁に変化する組織では、拡張性と柔軟性を重視したシステムが必要です。
この段階では、現実的な制約を踏まえつつ、最適な解決策を模索します。
⑤案を比較して採用する案を決める
複数の案を比較し、最も効果的かつ実現可能なものを選択します。その際、コスト、実装の容易さ、期待される効果などを考慮します。
例えば、初期コストは高くても、長期的に見て運用コストが低いソリューションを選ぶことが合理的な場合があります。また、ユーザーフレンドリーなインターフェースを持つシステムは、社内での受け入れやすさが高く、成功の確率を高めます。
⑥実装する
最終的に選ばれた案に基づいて、ファイル連携の実装を進めます。この段階では、適切なトレーニングやサポート体制の提供が重要です。
例えば、システム利用者を対象としたトレーニングセッションを実施し、新システムの使用方法を理解させることが必要です。また、運用段階での技術的な問題や疑問に対応するためのサポート研修やヘルプデスクの設置も考慮するべきです。
このようにして、スムーズな移行と高い利用率を確保することが、プロジェクトの成功につながります。
BizteXが提供するファイル連携サービス
BizteXは、単なるファイルの受け渡しや保存を自動化するツール提供にとどまらず、業務プロセス全体を設計し、運用から改善までを一気通貫で担うサービスを展開しています。ここでは、代表的なサービスを3つ取り上げ、その特徴を整理します。
BizteX Connect|クラウド間ファイル連携を支えるiPaaS

「BizteX Connect」は、クラウドサービスやSaaSアプリケーションをノーコードでつなぐiPaaSです。Salesforce・kintone・Slackなどの主要サービスとのAPI連携に加え、ファイルの受け渡しや保存を自動化するテンプレートも備えています。
システム部門に依存せず、現場担当者から導入可能で、データやファイルの転記・通知業務を自動化し、リアルタイムな情報共有を実現します。
BizteX robop|現場業務を補完するデスクトップ型RPA

「BizteX robop」は、PC操作を自動化するデスクトップ型RPAです。会計システムへのデータ入力や定型帳票の作成だけでなく、ファイルの分類・整理やアップロードといった作業も自動処理に置き換えます。
特に既存のオンプレミスシステムやクラウド非対応ツールとのファイル受け渡しと相性がよく、クラウド連携だけではカバーできない現場業務を補完します。
インテリジェント フロー|IPOを具現化する次世代サービス

インテリジェント フローは、BizteXが提供するIPO(インテリジェント・プロセス・オーケストレーション)をサービス化したものです。AI業務分析(インテリジェント マイニング)による課題特定をもとに、ファイル転送・保存・共有を含む最適な業務プロセスを設計し、自動化から運用・改善まで一気通貫で代行します。
既存システムとスムーズに連携できるため、現場の操作負担を取り除き、組織全体の業務を持続的に最適化します。
▼インテリジェント フローは下記のAI業務分析(無料)で課題と改善案を洗い出すところから始めます。
>>インテリジェント マイニング(AI業務分析)無料で試してみる
>>インテリジェント フローのサービスページ
▼より詳しく知りたい方は下記記事をチェック
まとめ|ファイル連携を活用し業務効率化を図ろう
ファイル連携は、システム間での大容量データのやり取りや、ファイルそのものをデータとして扱う業務に適した手段です。適切に導入することで、情報の一元化や検索時間の削減、入力ミスの防止などを実現し、業務効率を大きく向上させることができます。
BizteXが提供する「インテリジェント フロー」は、こうしたファイル連携を含む業務プロセス全体をAIと専門知識を組み合わせて設計・運用し、改善まで一貫して代行する次世代サービスです。単なるツール提供にとどまらず、企業ごとの業務特性に合わせた最適な仕組みを構築し、継続的な業務効率化を実現します。
「自社に最適なファイル連携の方法を知りたい」「業務全体の改善を包括的に進めたい」と考えている方は、ぜひインテリジェント フローをご検討ください。
▼"インテリジェント フロー"や"業務自動化"に関するご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。