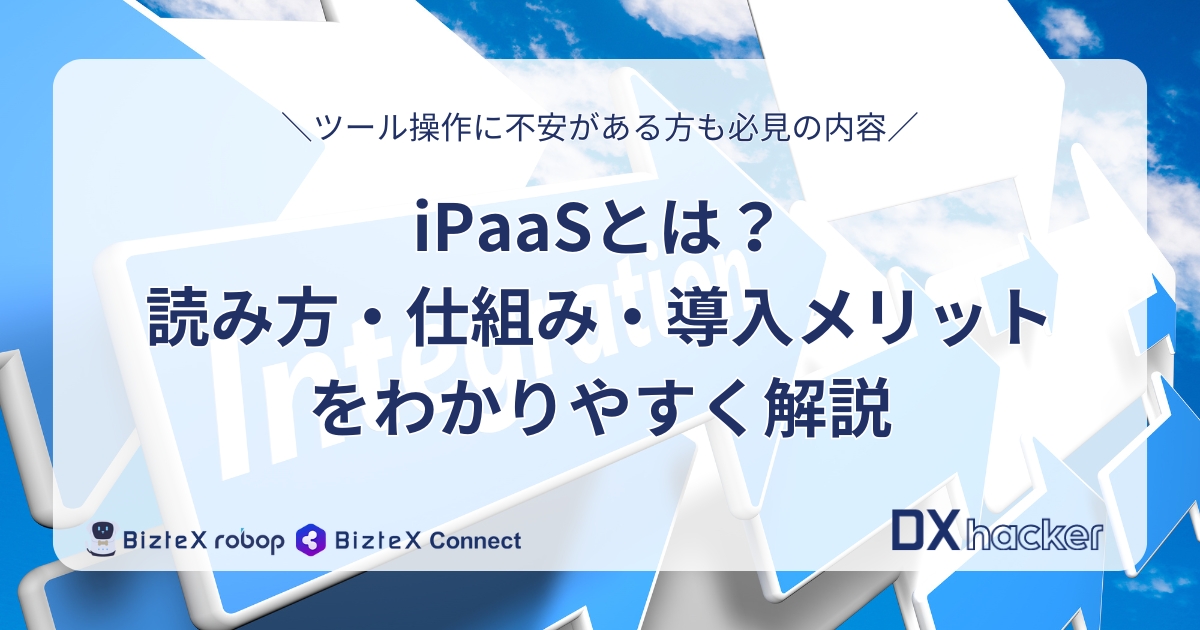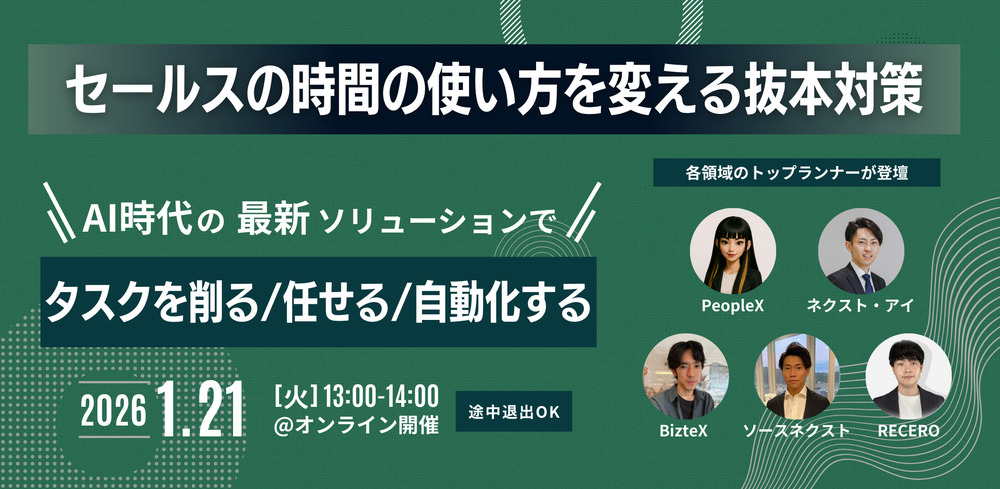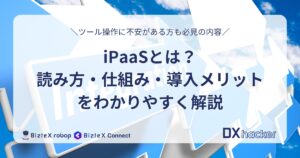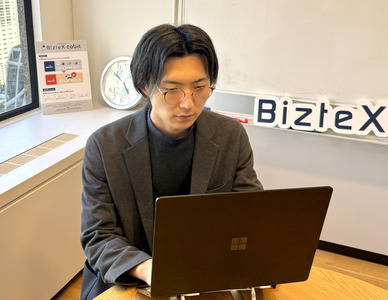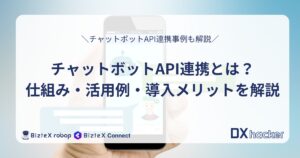クラウドサービスの利用が急速に広がる一方で、勤怠・会計・営業支援などのデータが分断され、二重入力や情報の不一致が発生しやすくなっています。
最近では、ChatGPTなどのAIを活用して業務を自動化しようとする動きも増えていますが、企業全体の業務を安定してつなぐには、より確実な仕組みが必要です。
こうした非効率を解消する基盤として注目されているのが iPaaS(アイパース) です。iPaaSは、システム間のデータ連携を自動化し、業務の正確性と効率性を高める中核基盤として、多くの企業で導入が進んでいます。
本記事では、iPaaSの基本的な仕組みから導入メリット、RPAやAIとの違い、さらに実際の活用例までをわかりやすく解説します。
- iPaaS(アイパース)の正しい意味と読み方
- iPaaSの仕組みと、RPA・ETL・AI連携との違い
- iPaaS導入によって得られる3つの主要メリット
- iPaaS導入で注意すべき課題と失敗を防ぐポイント
- BizteX Connect・BizteX robop・インテリジェント フローの活用法
iPaaSとは?読み方と基本定義
iPaaSとは Integration Platform as a Service の略で、複数のシステムやクラウドサービスをつなぐためのプラットフォームを指します。読み方は「アイパース」となり、誤って「アイパス」や「ipass」と表記されることもありますが正しくはiPaaSです。
従来、担当者がCSVを出力して別のシステムに手作業で取り込むといった煩雑な業務が多く存在しました。iPaaSを利用すれば、これらの作業をクラウド上で自動的に連携でき、業務のスピードと正確性を高めることができます。
iPaaSが生まれた背景
企業の業務は勤怠管理や会計、営業支援、マーケティングなど多様なシステムに分かれており、クラウドサービスの普及によってその数は急増しました。その結果、データが部門やツールごとに分断され、CSVの手作業転記や二重入力、照合作業といった非効率が顕在化しました。
RPAによる画面操作の自動化や個別のAPI開発は一時的な解決策となりますが、保守や拡張の負担が大きいのが現実です。こうした課題を根本的に解決し、持続的な業務効率化を実現するために登場したのがiPaaSです。
\さまざまなシステムとの連携が実現/
※今ならIT導入補助金制度を利用して、最大50%OFFで導入できます
iPaaSの仕組みとできること
iPaaSは、異なるシステムやクラウドサービス同士をつなぐための仲介基盤として機能します。あらかじめ用意された「コネクタ」と呼ばれる部品を利用し、条件(トリガー)と処理(アクション)を組み合わせることで、システム間のデータ連携を自動的に実行できます。これにより、担当者がCSVを取り出して別システムに取り込むといった手作業を大幅に削減できます。
また、ノーコード/ローコードで設定できるため、専門的なプログラミング知識がなくても運用が可能です。監視や通知機能も備わっており、データの受け渡し状況を可視化できる点も大きな特徴です。
RPA・ETL・個別API開発との違い
iPaaSは他の自動化手段とよく比較されますが、それぞれ得意分野や課題が異なります。RPAやETL、個別API開発の特徴を整理すると、iPaaSが担う“連携基盤”としての強みが見えてきます。
| 手段 | 得意領域 | 強み | 課題・弱点 |
|---|---|---|---|
| RPA | PC画面操作・ファイル処理 | APIがない業務でも自動化可能 | システム間連携や拡張性は弱い |
| ETL | データ抽出・加工・格納 | データ分析や基幹システム連携に強い | 業務フロー全体には不向き |
| 個別API開発 | 特定システム間の連携 | 高い柔軟性・自由度 | 開発・保守コストが大きい |
| iPaaS | 複数SaaS・システム間連携 | ノーコードで短期導入・拡張容易 | 製品によって連携範囲が異なる |
iPaaSは、RPAやETL、個別API開発に比べると「標準化された仕組みで持続的に運用できる」という点に優位性があります。特にSaaS利用が広がる現場では、ノーコードで素早く連携フローを構築でき、運用負荷を軽減できることが強みです。
代表的な活用ユースケース
iPaaSは、日常的な「システム間のデータ受け渡し」を自動化し、業務効率を大きく改善します。代表的な部門ごとの活用例をまとめると以下の通りです。
| 部門 | ユースケース例 | 効果 |
|---|---|---|
| 人事 | 勤怠データを給与計算ソフトへ連携/入社手続き情報を複数システムに登録 | 手作業の削減、入力漏れ防止 |
| 経理 | 請求書情報を会計システムに自動反映/発注データを在庫・会計と連携 | 二重入力防止、支払い漏れ防止 |
| 営業・マーケ | SFA・MAとSlackなどを連携し、顧客情報や商談ステータスを自動更新 | 対応漏れ防止、リード管理の効率化 |
こうしたユースケースは一部に過ぎませんが、共通するのは「異なるシステム間のデータを正確かつ自動で橋渡しする」という点です。現場担当者の工数削減に直結し、部門横断の情報活用を促進します。
今後は、AIによるデータ分析や要約などを組み合わせることで、より高度な自動化も実現可能です。
\「結局使われない…」業務ツールの悩み、もう終わりにしませんか?/
AIによるサービス連携とiPaaSの違い
ChatGPTやGeminiなどの生成AIの進化により、自然言語でワークフローを構築することも可能になりました。
AIを使えば、メールの要約やスプレッドシート更新など、シンプルな業務を自動化できます。
一方で、複数のSaaSを安定して連携させる本番運用には、iPaaSのほうが確実性が高いのが実情です。AIとiPaaSはいずれも業務効率化を目的としていますが、AIは柔軟な判断に、iPaaSは安定したデータ連携に強みがあります。
ここでは、まずAIによるサービス連携の特徴を整理し、その後にiPaaSとの違いを見ていきましょう。
AIによるサービス連携の特徴
AI連携とは、ChatGPTなどの生成AIを使って自然言語でサービスを操作したり、外部APIを呼び出してデータを処理したりする仕組みを指します。たとえば、「受信メールを要約してSlackに投稿して」と指示するだけで、AIがその処理を自動的に実行してくれます。
- コーディングなしで柔軟にタスクを実行できる
- 簡易的な情報処理やテキスト生成に強い
- 個人単位や小規模業務では導入ハードルが低い
一方で、AI連携は「柔軟であるがゆえの不安定さ」を抱えています。AIの出力は学習モデルや文脈に依存するため、同じ入力でも結果が変わることがあり、複数のSaaSをまたぐ安定的なワークフロー構築には課題が残ります。
そのため、AIによる連携は「アイデア検証(PoC)」や「一部補助的な業務」に向いているものの、重要データを扱う本番運用での再現性・管理性を求める場合はiPaaSのほうが適しています。
iPaaSによるサービス連携の特徴
一方、iPaaS(Integration Platform as a Service)は、複数のクラウドサービスや業務アプリを正確かつ安定的に接続・自動化するための専用基盤です。
各SaaSのAPIを正確に連携し、「Salesforce → kintone → Slack」や「ChatGPT → Google Drive → Teams」といった複数SaaS間の多段フローをノーコードで構築できます。
- 複数SaaSを安定的かつ再現性高く連携できる
- アクセス制御・ログ管理・エラー検知など、運用に必要な仕組みを標準搭載
- ISO/IEC 27001などのセキュリティ認証に準拠し、安全に業務へ導入可能
- ノーコードで構築できるため、IT部門だけでなく現場主導での改善も可能
このように、iPaaSはAIのような「考える力」ではなく、“確実に動かす力”を担う存在です。複数のSaaSを組み合わせた本番運用レベルのワークフロー構築には、iPaaSが最も安定した選択肢といえます。
AIとiPaaSの“使い分け”がポイント
AIとiPaaSは「どちらが優れているか」ではなく、役割を補完し合う関係です。
たとえば、AIが文書やメール内容を要約・分類し、その結果をiPaaSが確実にSaaSへ登録・通知する。このように役割を分担することで、AIの柔軟性 × iPaaSの安定性を両立できます。
AIが“考える部分”を担い、iPaaSが“確実に動かす部分”を支える構成。これこそが、企業が目指すべき実用的な自動化の形です。
BizteXでは、iPaaS「BizteX Connect」を中心に、AI連携とも親和性の高いフロー設計が可能です。AIを業務に取り入れたい企業こそ、まずは信頼できる連携基盤としてのiPaaSを導入することが、DX推進の第一歩となります。
iPaaS導入の主要メリット
iPaaSを導入することで、日常業務の非効率を解消し、システム間の連携を安定的に運用できる基盤を構築できます。
特に重要なのは「業務の自動化による時間創出」「データ活用の精度向上」「変化に強い柔軟な運用基盤」の3点です。いずれも、効率化だけでなく業務の“確実性”と“継続性”を高める効果があります。
業務の自動化による時間創出とヒューマンエラー防止
従来、システム間のデータ連携は、CSVの出力・加工・アップロードといった作業に依存しており、多くの時間と人手を要していました。iPaaSを導入すれば、これらの処理を一括で自動化でき、繰り返し発生する定型業務の工数を大幅に削減できます。
また、自動化によって手作業に伴う入力ミスや転記漏れといったリスクも解消。人が行う判断や分析に集中できる環境が整い、チーム全体の生産性を底上げします。
AIやスクリプトによる自動化に比べても、安定して同じ結果を再現できる点がiPaaSの強みです。
データ連携による精度向上と一元管理
業務データが部門やシステムごとに分断されていると、「どの数値が正しいのか」「最新の情報がどこにあるのか」といった混乱が生じます。iPaaSは複数のSaaSや社内システムをリアルタイムに連携し、データを自動で同期。常に最新かつ整合性の取れた情報を全社で共有できる環境を実現します。
これにより、営業と経理のデータ突き合わせやレポート集計などの手間が不要となり、経営判断のスピードと精度が向上します。また、AIやBIツールによる分析・活用の前提となる“正しいデータ基盤”を整える役割も果たします。
安定した拡張性と長期運用に強い基盤
業務で利用するクラウドサービスは日々アップデートされ、UIや仕様の変更も頻繁に発生します。RPAやスクリプトによる自動化では、こうした変更のたびにメンテナンスが必要になり、運用負担が増大しがちです。
iPaaSは、各サービスが提供する公式APIを介して連携する仕組みのため、画面構成やUI変更の影響を受けにくく、安定したデータ連携を長期的に維持できます。
また、ノーコードでフローの修正・拡張ができるため、仕様変更や新システムの追加にも柔軟に対応可能。システム構成の変化に強く、「一度作って終わり」ではなく継続的に使い続けられる運用基盤を構築できます。
導入でつまずきやすい課題
iPaaSは便利な仕組みですが、導入すれば必ず成功するわけではありません。要件定義の甘さや例外処理への対応不足、運用体制の不備などが原因で「思ったほど効果が出ない」「現場に負担が残った」といった失敗例も少なくありません。ここでは特につまずきやすい3つのポイントを整理します。
要件定義の粒度不足
iPaaS導入でよくある失敗が、要件定義の曖昧さです。「どのデータを、いつ、誰が、どこに渡すのか」といった流れを具体的に整理しないまま進めると、連携が不安定になったり、現場の期待と結果がずれることにつながります。
PoC(小規模検証)段階で詳細にフローを可視化し、対象範囲や例外条件を明確にすることが成功の鍵となります。
例外処理・エラーハンドリングの設計不足
業務には必ず想定外のケースが発生します。例えばシステムの通信エラーやデータ形式の不一致などがその典型です。
例外処理やエラーハンドリングを設計しないまま本格運用に入ると、現場が都度手作業で対応することになり、かえって負担が増えてしまいます。通知・リトライ・差分処理といった仕組みを事前に組み込むことで、安定した運用を実現できます。
運用体制・権限管理の不備
iPaaSは一度フローを作れば終わりではなく、システム追加や業務ルール変更に応じて調整が必要です。しかし運用体制や権限管理を明確にしていないと、属人化や管理不全が発生します。
誰が設定変更できるのか、監査ログをどう残すのかを初期段階で定めることが重要です。運用ルールを整備することで、トラブル発生時も迅速に対応できる体制を構築できます。
\AI×人の分析で、月間数百時間の削減実績も。/
RPA・iPaaS・IPOの使い分け
業務自動化の手段は複数ありますが、それぞれが得意とする領域は異なります。RPAはPC操作の自動化に、iPaaSはシステム間連携に強みを持ちます。そして、企業全体の業務を横断的に最適化するにはIPO(インテリジェント・プロセス・オーケストレーション)が有効です。
ここではBizteXが提供するサービスを例に、それぞれの特徴を整理します。
BizteX robop(デスクトップRPA)が向く領域

「BizteX robop」は、Excelや業務システムへの入力作業など、APIを持たないレガシー環境やデスクトップ操作を自動化できる国産RPAです。人が行うクリックや入力をそのまま再現できるため、既存システムを変えずに導入できるのが大きな特徴です。
特に「請求書データをシステムへ入力する」「基幹システムから特定データを抽出する」「定期的な帳票を作成して共有する」といった繰り返し発生する定型業務で高い効果を発揮します。
現場担当者が操作手順をそのまま自動化できる直感的な設計で、IT知識がなくても運用が可能。API連携が難しいオンプレミス環境や古いシステムが残る現場において、最小の投資で業務効率化を実現できるRPAとして多くの企業に選ばれています。
BizteX Connect(iPaaS)が向く領域

「BizteX Connect」は、ノーコードで複数のSaaSを安定的に連携できる国産iPaaSです。企業内に点在するSaaSをつなぎ、データの受け渡しや通知、更新といった処理を自動化することで、情報の分断を解消します。
特長は、プログラミング不要で誰でも安心してフローを構築できる操作性と、複数SaaSを安定的に接続できる再現性の高さ。たとえば、Salesforceで更新された顧客情報をkintoneに自動登録し、Teamsへ通知するなど、業務間をノンストップで連携させることが可能です。
さらに、ChatGPTやGemini、AI-OCRなどの外部AIサービスとも連携可能で、「柔軟性 × 安定性」を両立した自動化基盤として活用できます。セキュリティ認証(ISO/IEC 27001)も取得しており、企業の実務環境で安心して運用できる点も強みです。
社内リソースが足りない場合はIPO(インテリジェント フロー)

「インテリジェント フロー」は、業務全体の最適化を目指す企業に向けた次世代のプロセスオーケストレーションサービス(IPO)です。単なるツール提供にとどまらず、BizteXの専門チームが業務分析から設計・構築・運用までを一括で代行します。
導入前にはAIによる業務分析(インテリジェント マイニング)で現状課題を可視化し、ボトルネックを特定。導入後は「インテリジェント HUB」で成果や効果を数値化し、継続的な改善を支援します。
自社にIT人材がいない場合でも、“自動化を任せられる”運用代行型ソリューションとして活用できるのが特徴。無料プランからスタートできるため、まずは一部業務から段階的にIPOの効果を体感することができます。
無料プランで実現できる自動化事例(kintone × Notion × Slack 連携)

kintoneで新しいレコードが追加されると、その情報をNotionに自動反映し、Slackにも通知するフローをBizteX Connectで構築できます。これにより二重入力や登録漏れを防ぎ、チーム全体にリアルタイムで情報が共有されます。インテリジェント フローなら、このような業務フローを1つ無償で構築・改善できる無料プランから始められるため、導入負担なく効果を体感できます。
▼インテリジェント フローは下記のAI業務分析(無料)で課題と改善案を洗い出すところから始めます。
>>インテリジェント マイニング(AI業務分析)無料で試してみる
>>インテリジェント フローのサービスページ
▼より詳しく知りたい方は下記記事をチェック
\「ツールを使える人がいない」企業でも大丈夫!/
iPaaSを選定する際の観点
iPaaSを比較・検討する際には、細かい機能差を見る前に大きな3つの観点を押さえることが重要です。
| 観点 | 確認すべき内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 対応範囲(接続性) | 自社で使っているSaaSや基幹システムに対応しているか | 必須条件。特にオンプレや特殊システム対応の有無は要確認 |
| 運用しやすさ | 監視・通知・エラー処理・権限管理の仕組み | 日常運用の負担を左右するため、現場で扱いやすいかが重要 |
| 将来性(拡張性とコスト) | 条件分岐やデータ変換、従量課金の仕組み | 業務が増えてもスケールできるか、コストが膨らまないかを確認 |
選定時には「いま接続できるか」だけでなく、「運用を続けられるか」「将来も安心して拡張できるか」という視点が欠かせません。ここを押さえることで、導入後の失敗を防ぎやすくなります。
導入ステップ(スモールスタート)
iPaaSは一度に全社展開するよりも、まずは小規模に試す「スモールスタート」が成功の鍵です。現状の業務を整理し、効果が出やすい部分から導入することで、リスクを抑えながら成果を実感できます。
以下の3ステップを押さえるとスムーズに進められます。
まずは現状の業務フローを洗い出し、どこでデータの分断や手作業が発生しているかを明確にします。
勤怠データの転記や請求書処理など「繰り返し発生し、かつ担当者の負担が大きい業務」を優先候補にすると効果が出やすくなります。可視化の段階で関係部門を巻き込むことが、後の合意形成や運用定着にもつながります。
いきなり大規模に展開せず、1つの業務フローを対象にPoC(概念実証)を行います。実際にiPaaSを使ってフローを構築し、工数削減効果やエラー削減効果を定量的に確認することで、ROIを把握できます。
この段階で想定外の例外処理が洗い出されることも多く、本格導入前に課題を潰せる点もメリットです。
PoCで効果が確認できたら、本格運用に向けてフローの標準化ルールを整備します。具体的には「命名規則を統一する」「権限や承認フローを明確にする」「監視・通知の仕組みを設定する」といったルールです。
これにより属人化を防ぎ、トラブル時にも迅速に対応できる体制を作ることができます。
\業務の自動化、まずは無料で試しませんか?/
iPaaSでよくある質問(FAQ)
- iPaaSの正しい読み方は?
-
「アイパース」と読みます。誤って「アイパス」や「ipass」と表記されることがありますが正しくは iPaaS です。
- セキュリティは問題ないの?
-
各製品は通信の暗号化や認証機能を備え、外部からの不正アクセスやデータ漏洩を防ぐ仕組みを整えています。BizteXは情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格「ISO/IEC 27001 / JIS Q 27001」認証を取得しており、安全な運用体制のもとでサービスを提供しています。
- 既存の基幹システムやオンプレ環境とも連携できる?
-
多くのiPaaSはクラウドサービスに強みがありますが、オンプレやレガシー環境もコネクタやRPAとの組み合わせで対応可能です。BizteX Connectは国産製品のため国内システムとの親和性も高いです。
- RPAとどう使い分ければいい?
-
RPAはPC操作の自動化、iPaaSはシステム間のデータ連携に強みがあります。CSV転記や画面操作が残る部分はBizteX robop(RPA)、SaaS同士の連携はBizteX Connect(iPaaS)と併用するのが効果的です。
- AIでワークフローを作れるなら、iPaaSはもういらない?
-
AIは柔軟な処理が得意ですが、複数のSaaSを安定して連携させるにはiPaaSが適しています。各サービスのAPIを正確に接続し、権限管理やエラー制御まで行えるため、実務で安心して運用できる自動化基盤となります。
- コストを抑えて試す方法はある?
-
BizteX Connectは1週間の無料トライアルで機能を体験できます。
一方、インテリジェント フローはBizteX Connectを用いた1業務フローの構築・改善をプロが代行し、ずっと無料で利用できるプランを提供しています。現場の運用負担なく、自動化効果を継続的に確かめながら導入を検討できます。
まとめ|iPaaSを理解し、自社に合ったDX推進を
iPaaSは、クラウドサービスや社内システムをシームレスにつなぎ、手作業の削減とデータ精度の向上を支える“業務自動化の中核基盤”です。正しく設計・運用すれば、日々のルーティン業務を確実に効率化し、全社のDX推進を加速させることができます。
現場のPC操作を自動化したい場合は「BizteX robop」、複数SaaSやシステム間を安定して連携させたい場合は「BizteX Connect」が有効です。さらに、「運用を任せたい」「業務全体を最適化したい」という企業には、専門チームが構築・改善を代行する「インテリジェント フロー」が最適です。
自社の課題やリソースに合わせて最適な方法を選び、無料から始められる自動化で、確実にDXを前進させましょう。
▼"インテリジェント フロー"や"業務自動化"に関するご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。